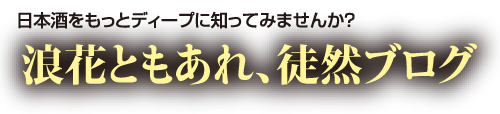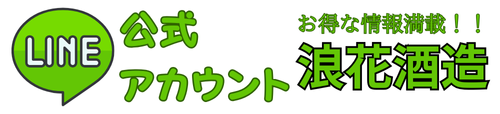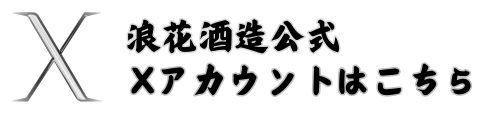新着お知らせ・日本酒豆知識・雑感

大阪府で最も歴史のある(創業1716年)浪花酒造の現社長、成子和弘による日本酒の知識・雑観・評判等について記載したブログです。
成子和弘は昭和62年(1987年)に浪花酒造に入社。
平成10年(1998年)に10代目として代表取締役に就任。
約35年、日本酒製造業界で従事した日本酒のエキスパート。
日本酒だけでなく、酒類全般の知識も豊富。
日本酒事業に従事したエキスパートの観点から、ご覧頂いている皆様に還元できる日本酒で躓きそうなポイントや雑学、日々の所感・新着・イベント・出店情報・酒ディプロマの勉強・対策等を更新。
ブログ記事一覧は下記
宴会幹事さんの仕事
日本酒の味に濃淳や淡麗があるように、ビールにも濃淳や淡麗がある。
最近発売されたキリンの「豊潤」というビール、本当に濃淳で味わいがあったので驚いた。
キリンラガーより値が高いが美味しい。
今までのビール業界は、
オリンピック卓球女子
オリンピックの卓球女子、開幕前からマスコミでよく取り上げられていたので、とても期待して見ていた。
事実、香港相手に軽々と勝っているのを見て、これなら優勝候補の中国にも勝てるだろうと予想していた。
真夏のビン詰め作業
お酒の仕込みは11月~3月の寒い時期だが、ビン詰め作業はその商品の在庫が減ってきたら随時行なう。
今日は「特別純米辛口」のビン詰め作業を行なった。
お酒は65℃~70℃に加熱殺菌してからビン詰めする。
するとビンのフタを開けなければ何年経っても腐らない。
ブームの循環
今日は大阪市内の業務用酒販店の方と一緒に、昼間から立ち飲み営業しているミナミの繁盛店に行った。
繁華街にあるので、昼間からアルコールを飲んでるお客さんが多い。
一番売れるのはもちろんビールだが、その次はブームによって変わる。
吟醸酒じゃないのに吟醸酒の味
吟醸酒の定義は、酒米を60%以上精米した米(玄米重量の60%以下まで精米した米)で仕込んだ酒だ。
玄米の周囲の黄土色部分は脂肪やたんぱく質、中心付近の白い部分が純粋なデンプン。
周辺部分の脂肪やたんぱく質は、お酒にとって雑味のもとになり、純粋なデンプンで仕込むと雑味のないきれいな酒になる。