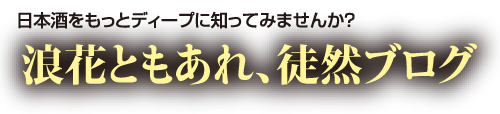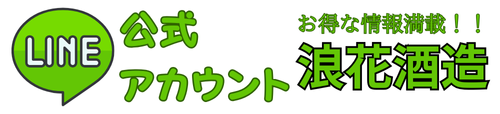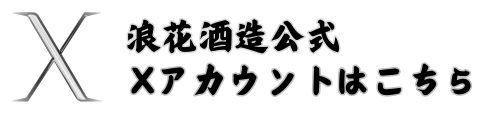新着お知らせ・日本酒豆知識・雑感

大阪府で最も歴史のある(創業1716年)浪花酒造の現社長、成子和弘による日本酒の知識・雑観・評判等について記載したブログです。
成子和弘は昭和62年(1987年)に浪花酒造に入社。
平成10年(1998年)に10代目として代表取締役に就任。
約35年、日本酒製造業界で従事した日本酒のエキスパート。
日本酒だけでなく、酒類全般の知識も豊富。
日本酒事業に従事したエキスパートの観点から、ご覧頂いている皆様に還元できる日本酒で躓きそうなポイントや雑学、日々の所感・新着・イベント・出店情報・酒ディプロマの勉強・対策等を更新。
ブログ記事一覧は下記
瓦の葺き替え終了
令和元年10月、日本に上陸した台風19号、全国各地に甚大な被害をもたらした。
あちこちの大きな河川が決壊し浸水、なんと全国で10万軒の家屋に被害にあった。
瓦が飛ばされた家屋も多く、台風通過後多くの家の屋根がブルーシートで覆われた。
浪花酒造の酒蔵と本宅の瓦も2tトラック3台分飛ばされた。
水素エンジン
昨日今日と富士24時間耐久レースに知り合いが出場したので、富士スピードウエイに応援に行ってきた。
エンジン排気量の違いで5つの部門があり、知り合いは彼の属する部門で見事2位に入賞した。
きき酒と晩酌
一般的なきき酒の方法はお酒を口に含んだあと、口から軽く息を吸い込み、ズルルと音を立てお酒が舌全体に行き渡るようにし味を見そのあと吐き捨てます。
飲むと酔ってしまって味がわからなくなるからです。
舌先は甘味を感じる部分、舌の両端は苦みを感じる部分、舌の奥は辛さを感じる部分など、感じる部位が分かれているので舌全体に行き渡るようにして総合的な判断をしています。
奈良漬も販売中
浪花酒造でできた酒粕を貝塚市の奈良漬会社、辻漬物さんに納めている。
そこでできた奈良漬を弊社の直売所でも販売している。
なかなか好評で、奈良漬だけを購入に来るお客さんも大勢おられる。
リサイクルの優等生
昨今、限りある資源の有効活用があちこちで叫ばれています。
一般には知られてませんが、お酒(日本酒と焼酎)の一升ビン、もう何十年も前から日本ではほぼ9割がリサイクルされています。
なぜ日本でコロナワクチンができないのか?
今日はお酒の話題じゃなく、コロナワクチンについて。
みなさん不思議に思いませんか?
優秀な人材がいっぱいいる日本で、なぜコロナワクチン開発できないのか?
なぜ外国頼みなのか?
大阪府の酒蔵
大阪府に酒蔵が十数社あるのだが、ほとんど知られていない。
大阪市内の料飲店でも大阪の地酒を扱っている店は少ない。
日本酒に興味をお持ちのネット関連の会社の社長さんが、「大阪市内の料飲店で大阪の地酒をほとんど見ないのが寂しい。もっと知ってもらえるようお手伝いをしたい」と、今日弊社に訪ねて来られた。
大阪府の地酒メーカーは、社員数人程度の小さな蔵が多い上、大阪市内から離れた市や町にある。
また、灘や伏見の大手メーカーに挟まれ存在感がない。
ただ大阪府の酒蔵同士は仲が良く、月に1度は集まってお酒のアピール方法や品質向上の仕方など話し合い、いろんなイベントも行なっている。
悪酔いの原因と対策
お酒を飲んでいる途中で、頭痛、吐き気、寒気、イライラなど気分が悪くなる事を悪酔いと言います。
よく、いろんなお酒をチャンポンすると悪酔いするとか、日本酒を飲むと悪酔いするとか言われます。
お酒のチャンポンが悪酔いの原因なら、いろんな種類のお酒をおさじ一杯ずつ飲んでも悪酔いするのかって事です。