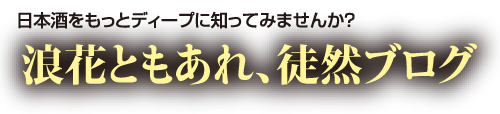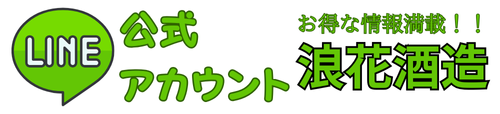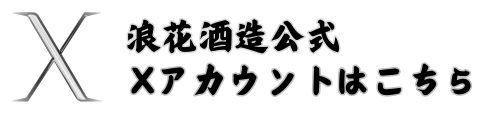新着お知らせ・日本酒豆知識・雑感

大阪府で最も歴史のある(創業1716年)浪花酒造の現社長、成子和弘による日本酒の知識・雑観・評判等について記載したブログです。
成子和弘は昭和62年(1987年)に浪花酒造に入社。
平成10年(1998年)に10代目として代表取締役に就任。
約35年、日本酒製造業界で従事した日本酒のエキスパート。
日本酒だけでなく、酒類全般の知識も豊富。
日本酒事業に従事したエキスパートの観点から、ご覧頂いている皆様に還元できる日本酒で躓きそうなポイントや雑学、日々の所感・新着・イベント・出店情報・酒ディプロマの勉強・対策等を更新。
ブログ記事一覧は下記
大阪市立大学ソーシャルイノベーションコースのPR動画に当社が登場します
大阪市立大学ソーシャルイノベーション コースのPR動画に当社が登場します。
大阪市立大学さんが当社にフィールドワークに来られた際に撮影されたものが使われています。
麹(こうじ)と酵母(こうぼ)
日本酒の製造過程、麹カビと酵母という2種類の菌が使われる。
こうじとこうぼ、言葉の感じが似ているので混同されている方が多いが、全く別の菌であるし働きも全然違う。
麹カビは、お米のデンプンを糖分に変える働き。酵母は、その糖分をアルコール(お酒)に変える働きをする。
いいお酒を造るには、
無我無心

弊社のお酒で、一升瓶1本1万円の「無我無心」という酒がある。
15年前に初めて1万円の酒を発売した時につけた名前だ。
高級酒を作った場合、メイン銘柄(浪花正宗)とは違う名前を付ける蔵が多い。
私も、高級感があり日本酒らしい名前がないかいろいろ考えていた。
ちょうどその頃、地下鉄 淀屋橋駅で書道展をやっていて、いっぱい「書」が貼りだされていた。
何とはなく見ていたが、その中のひとつ「無我無心」という文字とその雰囲気にとても惹かれた。
無我無心とは、
大手メーカーの酒はブレンド酒?
昭和時代、灘や伏見の大手メーカーの酒はとても人気で、自社の製造だけでは追い付かず、中小の蔵からお酒を買い集めそれらをブレンドして販売していた。
しかし、日本酒の需要は昭和48年(1973年)をピークにどんどん減ってゆき、現在ではほぼ3分の1になっている。
女性ファン
日本酒には見向きもしなかった女性ファンが年々増えてきてるのがうれしい。
吟醸や大吟醸はフルーティーでほんのり甘く女性好みの味だからだ。
日本酒のイベントでも最近はその参加者の半数が女性だ。
見ていると一般的に男性はお酒の味にあまり興味ない。
お酒に酔ってみんなでワイワイやるのが目的。
女性はお酒の味そのものに興味があり、このお酒は香りがいいとか、甘いとか飲みやすいとか、しっかり味の評価をしている。
ストップウォッチ
日本酒の中で一番の高級品は大吟醸です。
大吟醸は酒米を50%以上削ってしまうので、もちろん原料代が高いです。
それ以上に他の酒に比べ、手間がかかりまた技が必要だからです。
人気が9割
売れるお酒とは人気ある酒。
日本酒はどれも透明の液体なので、視覚でこれは美味しいとか判断できない。
ビン形やラベルデザインで選ぶ人もいるが、ネットランキングで上位だ、きき酒専門家が美味しいと言った、有名タレントが宣伝しているなどの人気で選ぶ人が圧倒的だ。
そのような人気銘柄の酒とそうでない酒、よく目隠しで飲みどれだけ違うのか確かめている。
連休中の人気商品
この連休中、直売所ずっと営業していたが、予想以上に来客に恵まれた。
近くのイオンモールやアウトレットが緊急事態宣言で営業していなかったので、そのお客さんが流れて来てくれたのかも。
一番の人気商品は
酒の器
同じお酒を飲むのでも、どんな器で飲むかによって美味しさが違います。
普通酒(燗酒)がメインだった頃は、猪口(ちょこ)という50mlほどの小さな陶器の器で飲んでいました。
なぜこんなに少量なのか?
昔は宴会時、各自、猪口を持って宴会参加者全員とお酒を酌み交わすという習慣がありました。
小さい器でないとすぐに酔ってしまうからです。
でも、華やかな香りを楽しむ吟醸酒や大吟醸などは、小さな器だと香りを楽しめません。
吟醸酒や大吟醸はワイングラスで飲むのが一番だと思います。
ただワイングラスは値段が高いし、洗浄もやっかいで、ちょっと油断するとすぐに割れてしまいます。
私が日頃使っている器は、